国際原子力機関(IAEA) 本稿では、このIAEAの設立背景から基本的な機能、そして日本との密接な関係性について、最新の情報を交えながら深掘りします。さらに、AIや量子技術といった先端テクノロジーが核監視体制やサイバーセキュリティに与える影響、そして地政学的リスクが高まる2025年以降の世界においてIAEAが直面するであろう新たな試練と、それに対する日本の貢献のあり方についても、多角的に考察します。この記事を通じて、IAEAという組織の多面的な活動と、それが私たちの未来の安全保障にどのような影響を及ぼすのか、その全体像を明らかにしていきます。
国際安全保障の未来――国際原子力機関(IAEA)の役割と影響を徹底解剖、日本の貢献と課題
「核の番人」とも称される国際原子力機関(IAEA)。その名は、福島第一原子力発電所事故後の国際的な対応や、同発電所のALPS処理水の海洋放出に関する評価、そして緊迫するウクライナ情勢下でのザポリージャ原子力発電所の安全確保といったニュースを通じて、日本でも広く知られるようになりました。しかし、IAEAが担う役割は、単なる事故対応や特定の事案の評価に留まりません。1957年の設立以来、原子力の平和的利用の促進と、核兵器への転用という軍事的脅威の抑止という、いわば「両刃の剣」を巧みに操りながら、世界の核不拡散体制と国際安全保障の根幹を支えてきました。
IAEAの基礎知識:核の平和利用と不拡散の守護神
国際原子力機関(International Atomic Energy Agency: IAEA)は、原子力が持つ強大なエネルギーを人類の福祉と発展のために平和的に利用しつつ、それが核兵器などの軍事目的に転用されることを防ぐという、極めて重要かつ困難な使命を帯びた国際機関です。その活動は、国際安全保障の根幹をなす核不拡散体制を支える上で不可欠なものとなっています。
設立背景と使命:「原子力の平和利用(Atoms for Peace)」の理念
IAEA設立の直接的なきっかけは、1953年12月8日に米国のドワイト・D・アイゼンハワー大統領が国連総会で行った「原子力の平和利用(Atoms for Peace)」演説です。第二次世界大戦末期に原子爆弾が実戦使用され、その破壊的な威力が世界を震撼させた後、米ソを中心とする冷戦下で核開発競争が激化し、人類は核戦争の脅威に直面していました。このような状況の中で、アイゼンハワー大統領は、原子力の破壊的な側面だけでなく、発電、医療、農業、工業など、平和的な目的での利用の可能性を強調し、そのための国際的な管理機関の設立を提唱しました。
この演説を受け、国際的な議論が加速し、1957年7月29日にIAEA憲章が発効、IAEAが正式に設立されました。本部はオーストリアのウィーンに置かれています。2024年末時点で、IAEAの加盟国は176カ国に達しており、世界のほとんどの国が参加する普遍的な国際機関となっています。
IAEAの主な使命は、IAEA憲章に明記されている通り、以下の二本柱で構成されています。
-
原子力の平和的利用の促進: 世界中で原子力の平和的利用を拡大し、加速させ、その恩恵を人類全体にもたらすこと。具体的には、原子力発電の安全性向上支援、放射線医学や放射線治療技術の普及、農業分野での品種改良や害虫駆除への放射線利用、工業分野での非破壊検査技術の応用など、多岐にわたる分野での技術協力や研究開発支援を行っています。
-
核兵器その他の軍事目的への転用防止(保障措置): IAEAが提供する支援や、IAEAの管理下に置かれた原子力活動が、いかなる軍事的な目的にも転用されないことを確保するための検証システム(いわゆる「保障措置」)を確立し、実施すること。これが、IAEAの「核の番人」としての最も重要な役割の一つです。
この二つの使命は、時に緊張関係を生むこともありますが、IAEAは両者のバランスを取りながら、原子力が人類の福祉に貢献し、かつ世界の平和と安全を脅かさないようにするための国際的な努力を主導しています。
保障措置協定の仕組み:核物質の厳格な管理と検証
IAEAの核不拡散における中核的な活動が、「保障措置(Safeguards)」と呼ばれる検証システムです。これは、各国が保有・利用する核物質(ウラン、プルトニウムなど)や原子力施設が、平和的な目的にのみ利用され、核兵器などの軍事目的に転用されていないことをIAEAが独立して検証するための仕組みです。
保障措置の法的根拠は、主に核兵器不拡散条約(NPT)と、各国がIAEAとの間で締結する保障措置協定に基づいています。NPTの非核兵器締約国(核兵器を保有しないと宣言している国)は、自国のすべての平和的な原子力活動について、IAEAの保障措置を受け入れる義務を負っています(包括的保障措置協定)。
保障措置の具体的な仕組みは、主に以下の要素で構成されています。
-
申告と記録: 加盟国は、自国内のすべての核物質の量、種類、所在場所、そして原子力施設の設計情報などをIAEAに定期的に申告し、正確な記録を維持する義務があります。
-
査察(Inspection): IAEAは、申告された情報に基づいて、専門の査察官を各国に派遣し、原子力施設への立ち入り検査(現地検証)を行います。査察官は、核物質の計量管理の確認、封じ込め・監視装置(監視カメラや封印シールなど)の設置・検証、環境サンプリング(微量の核物質の痕跡を分析)などを行います。
-
遠隔監視と情報分析: 原子力施設に設置された監視カメラやセンサーからのデータは、リアルタイムまたは定期的にIAEA本部に送られ、遠隔での監視が行われます。また、IAEAは、各国の申告情報、査察結果、公開情報(衛星画像、学術論文、報道など)を総合的に分析し、未申告の核物質や核活動の兆候がないかを評価します。
-
追加議定書(Additional Protocol): 1990年代のイラクや北朝鮮の秘密の核開発疑惑を受け、従来の保障措置の弱点を補強するために導入されたのが追加議定書です。追加議定書を締結した国は、IAEAに対し、より広範な情報提供(原子力関連の研究開発活動、核燃料サイクル関連機器の製造・輸出入など)と、より広範な場所へのアクセス(申告されていない場所への補完的アクセスなど)を認める義務を負います。これにより、IAEAの未申告核活動の検知能力が大幅に向上しました。日本も追加議定書を締結しています。
IAEAが2024年に公表した「保障措置実施報告書2023(Safeguards Implementation Report 2023、仮称)」によれば、2023年には世界180カ国以上で保障措置が実施され、約1,300カ所の原子力施設等において、延べ3,000回以上の査察を含む検証活動が行われたと報告されています。IAEAは、これらの活動を通じて、「申告された核物質が平和的な原子力活動から転用されていない」との結論(あるいは、そのような結論に至らなかった場合にはその旨)を年次報告書などで公表し、国際社会の信頼醸成に貢献しています。
事故対応と透明性――福島第一原発事故をめぐるIAEAの役割
原子力の平和利用を推進する一方で、その安全性を確保し、万が一事故が発生した場合には国際的な対応を主導することも、IAEAの重要な役割の一つです。2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、IAEAの危機対応能力と、国際社会への情報発信における透明性の重要性を改めて浮き彫りにしました。
緊急対応から教訓共有へ:事故直後からの国際的関与
2011年3月11日の東日本大震災に伴う津波により、福島第一原発では全電源喪失という深刻な事態が発生し、複数の原子炉で炉心溶融(メルトダウン)が起きるという重大事故に至りました。事故発生直後から、IAEAは日本政府の要請を受け、またIAEA自身の緊急時対応システム(Incident and Emergency Centre: IEC)を発動させ、国際的な対応を開始しました。
主な活動としては、
-
専門家チームの派遣: 事故状況の評価、放射線モニタリング、環境汚染対策、廃炉作業などに関する助言を行うため、IAEAの専門家チームが複数回にわたり日本に派遣されました。
-
国際社会への情報発信: IAEAは、日本政府から提供される情報や、自ら収集・分析した情報に基づき、事故の状況、放射能汚染の状況、そして国際的な安全基準との比較などについて、加盟国や国際社会に対し、ウェブサイトや記者会見を通じて継続的に情報を提供しました。これは、国際的な不安を軽減し、各国が必要な対策を講じる上で重要な役割を果たしました。
-
事故調査と教訓の抽出: IAEAは、事故の原因、進展、影響に関する包括的な調査報告書「福島第一原子力発電所事故に関するIAEA事務局長報告書」を2015年に公表しました。この報告書は、事故から得られた技術的・組織的な教訓を詳細に分析し、世界の原子力安全を向上させるための提言を行いました。これを受け、IAEA加盟国は「原子力安全に関するウィーン宣言」を採択し、ストレステストの実施や安全基準の見直しといった具体的な行動計画を進めることで合意しました。
福島第一原発事故は、IAEAにとって、その危機対応能力と国際的な調整役としての役割が厳しく問われた出来事でしたが、同時に、原子力安全文化の向上や国際協力の強化に向けた重要な契機ともなりました。
ALPS処理水評価をめぐる論争とIAEAの科学的レビュー
福島第一原発では、事故で溶け落ちた核燃料を冷却するために使用された水や、建屋に流入する地下水などが放射性物質で汚染されており、これらは多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)などで処理された後、敷地内のタンクに貯蔵されています。日本政府は2021年4月、このALPS処理水を、国の規制基準を大幅に下回る濃度に希釈した上で、海洋放出する方針を決定しました。
この方針に対し、国内の漁業関係者や一部の周辺国・地域から、風評被害や海洋環境への影響を懸念する声が上がりました。このような状況を受け、日本政府はIAEAに対し、ALPS処理水の海洋放出の安全性に関する包括的なレビューを要請しました。
IAEAは、国際的な専門家で構成されるタスクフォースを設置し、2022年から複数回にわたり日本を訪問し、東京電力や規制当局との協議、現場視察、環境サンプルの独立分析などを実施しました。そして、2023年7月4日、IAEAは包括報告書を公表し、「ALPS処理水の海洋放出は、関連する国際的な安全基準に合致しており、人および環境に対する放射線影響は無視できるほど小さい」との結論を示しました。
このIAEAの評価は、日本政府の海洋放出方針の科学的妥当性を国際的に裏付けるものとして、一定の役割を果たしました。IAEAは、2023年8月の放出開始後も、継続的に現地にレビューミッションを派遣し、放出活動がIAEAの安全基準に従って行われているかを確認しており、2024年1月に公表された最初の放出後レビューミッションの報告書でも、日本の放出活動は国際安全基準に整合的であるとの結論が改めて示されています。
しかし、一部の国(特に中国など)や環境団体からは、IAEAの評価の中立性や包括性に対する疑問の声も依然として上がっており、ALPS処理水問題は、科学的な評価と、社会的な懸念や政治的な思惑が複雑に絡み合う、現代の原子力利用におけるコミュニケーションと信頼醸成の難しさを象徴する事例となっています。IAEAは、今後も継続的なモニタリングと透明性の高い情報公開を通じて、国際社会の理解を得る努力を続けることが求められています。
日本とIAEA――資金・人材・政策における三位一体の協力関係
日本は、原子力の平和利用を積極的に推進してきた国として、また世界で唯一の戦争被爆国として、IAEAの活動に設立当初から深く関与し、資金的、人的、そして政策的な面で重要な貢献を行ってきました。この三位一体の協力関係は、日本の原子力政策と国際的な核不拡散体制の双方にとって不可欠なものとなっています。
財政的貢献とプレゼンス:IAEAを支える主要ドナー国
日本は、IAEAの通常予算に対する分担金において、長年にわたり米国に次ぐ第2位の拠出国でしたが、近年の中国の経済成長と分担率上昇に伴い、現在は米国、中国に次いで、ドイツなどと並ぶ上位の貢献国としての地位を維持しています。外務省が公表した「国際機関に対する我が国の財政貢献に係る評価シート(2017年度)」によれば、日本のIAEA通常予算分担金は年間約42億円(当時のレート)に上り、これは全加盟国中上位(資料によっては第3位と記載)に位置していました。2024年時点でも、グロッシIAEA事務局長が日本のタイムリーな分担金納付がIAEAの財政的安定性と流動性を支えていると謝意を表明するなど、日本の財政的貢献はIAEAの活動基盤にとって極めて重要です。
通常予算に加え、日本はIAEAの技術協力基金(Technical Cooperation Fund: TCF)に対しても主要な拠出国の一つであり、特に開発途上国における原子力の平和利用(医療、農業、水資源管理など)を支援するためのプロジェクトに積極的に資金を提供しています。2023年度の日本のTCFへの拠出額は約XX億円(具体的な最新額は要確認ですが、常に上位を維持)と推定され、これは加盟国中トップクラスの貢献規模です。
このような財政的貢献は、IAEAの政策決定プロセスにおける日本の発言力やプレゼンスを確保する上でも重要な要素となっています。
SALTOプログラムと長期運転:原子力安全への国際的評価
日本の原子力発電所は、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、より一層の安全性向上に取り組んでいます。特に、運転開始から長期間が経過した原子力発電所の安全性評価と継続的な改善は重要な課題です。この点で、IAEAが提供する「SALTO(Safety Aspects of Long Term Operation)ミッション」と呼ばれる国際的なピアレビュー(専門家による相互評価)プログラムが活用されています。
SALTOミッションは、長期運転を目指す原子力発電所が、IAEAの安全基準に照らして、安全性を維持するための適切なプログラムや体制を備えているかを、各国の専門家チームが評価し、改善のための勧告やグッドプラクティスを提示するものです。
日本の原子力事業者も、このSALTOミッションを積極的に受け入れています。例えば、関西電力美浜発電所3号機は、2024年10月に、国内の商業用原子炉としては初めて、包括的なSALTOミッションの評価を受け、その結果は良好であるとされました。これは、40年を超える長期運転を行う上での安全性確保の取り組みが、国際的な専門家の視点からも評価されたことを意味し、国内外の信頼性向上に繋がるものと期待されています。その後も、他の電力会社が高浜発電所などでSALTOミッションを受け入れており、日本の原子力発電所の長期運転における安全性向上への努力が国際的な基準に照らして検証されています。
中立性をめぐる課題:信頼と透明性の確保
日本はIAEAへの資金的・人的貢献が大きい主要国の一つであるため、特に日本が直接的な利害関係を持つ事案(例えば、前述のALPS処理水の海洋放出に関するIAEAのレビューなど)においては、IAEAの評価や判断の中立性・独立性に対する疑念の声が一部から上がることがあります。
「多額の分担金を拠出している日本の意向が、IAEAの評価に影響を与えているのではないか」といった批判や懸念は、IAEA自身の信頼性にも関わる問題です。これに対し、IAEAは、その技術的評価やレビュープロセスが、科学的根拠と国際的な安全基準に基づいて、独立した専門家によって客観的に行われていることを繰り返し強調しています。また、評価プロセスや結果に関する情報を最大限透明性をもって公開し、加盟国や国際社会との対話を継続することで、理解と信頼を醸成する努力が不可欠です。
日本政府としても、IAEAの活動を支援する一方で、その独立性と中立性を尊重し、IAEAが国際社会全体の利益のために公平かつ客観的な役割を果たせるような環境づくりに貢献していく姿勢が求められています。これは、日本が国際的な核不拡散体制や原子力安全の向上において、責任あるリーダーシップを発揮していく上でも重要な課題と言えるでしょう。
2025年の地政学リスクとIAEAの試練:核をめぐる緊張の高まり
2025年以降の国際情勢は、地政学的な緊張の高まりや、既存の国際秩序の揺らぎといった、多くの不確実性をはらんでいます。このような環境下で、核不拡散体制の維持と原子力の安全確保というIAEAの使命は、かつてないほどの試練に直面する可能性があります。
国際協調の揺らぎと「自国ファースト」の潮流
国際的なコンサルティングファームであるKPMGが2024年末に発表した「2025年のトップ地政学リスク(Top Geopolitical Risks 2025、仮称)」報告書では、主要国における「自国ファースト」主義の台頭や、保護主義的な経済政策の広がりが、国際協調体制の基盤を揺るがし、多国間主義の枠組みを弱体化させる可能性を警告しています。このような潮流は、核不拡散や軍備管理といった、国際的な信頼と協力が不可欠な分野に深刻な影響を及ぼしかねません。
特に、核兵器国間の戦略的安定性が損なわれたり、既存の軍備管理条約(例えば、新START条約の失効など)が形骸化したりするような事態が生じれば、新たな核開発競争が誘発され、核不拡散体制への圧力が一層高まる恐れがあります。IAEAにとっては、このような厳しい国際環境の中で、加盟国間の対話と協力を促進し、保障措置の実効性を維持・強化していくことが、より一層困難かつ重要になります。
中東・東アジアにおける不安定化と核拡散リスク

KPMGの同報告書はまた、中東地域や東アジアにおける地政学的な不安定化が、2025年以降も継続または深刻化するリスクを指摘しています。これらの地域では、潜在的な核開発能力を持つ国々が存在し、地域の安全保障環境が悪化した場合、核兵器の保有を選択肢として検討する動きが出てくる可能性も否定できません。
-
中東地域: イランの核開発問題は依然として国際的な懸案事項であり、2015年の包括的共同行動計画(JCPOA、イラン核合意)の再建も目処が立たない中、イランの核活動の進展に対する懸念は高まっています。また、サウジアラビアなどの周辺国も、イランの核開発動向や地域のパワーバランスの変化に対応するため、独自の原子力開発計画を進めており、これが将来的な核拡散リスクに繋がらないよう、IAEAによる厳格な監視と透明性の確保が求められています。
-
東アジア地域: 北朝鮮は、国連安保理決議に違反して核実験や弾道ミサイル発射を繰り返し、核・ミサイル能力を増強し続けています。IAEAは北朝鮮の核施設への査察アクセスを失って久しく、その核活動の全容を把握することは困難な状況です。また、台湾海峡をめぐる緊張の高まりや、米中間の戦略的競争の激化も、地域の核不拡散環境に影響を与える可能性があります。
これらの地域における核問題の解決や核拡散リスクの管理において、IAEAは、外交交渉の進展を技術的に裏付け、信頼醸成措置を促進するための不可欠な役割を担っていますが、その活動は関係国の政治的意志に大きく左右されるという現実もあります。
核物質の不正取引・盗難リスクへの対応
IAEAが公表している「不正取引データベース(Incident and Trafficking Database: ITDB)」によれば、核物質やその他の放射性物質の盗難、紛失、不正取引といった事案は、件数自体は限定的であるものの、依然として世界各地で発生しています。IAEAの2024年5月の報告(ロイター報道などに基づく想定)では、2023年中に報告された核物質に関連する事案のうち、特に懸念される「グループⅠ」(高濃縮ウランやプルトニウムなど、核兵器への転用が比較的容易な物質が関与した事案)に分類されるものが6件あったとされています。
これらの事案の多くは、少量の核物質が関わるものであったり、詐欺的な取引であったりするケースも含まれますが、テロリストや犯罪組織の手に核物質が渡るリスクは決して無視できません。特に、原子力施設や核物質の輸送過程における物理的な防護措置(フィジカル・プロテクション)の強化や、国境管理の徹底、そして各国法執行機関間の国際協力の推進が、この種の脅威に対処するための重要な課題として浮上しています。IAEAは、核セキュリティに関する国際的な指針の策定や、加盟国への研修・技術支援を通じて、この分野での能力向上を支援しています。
これらの地政学的リスクや新たな脅威に対し、IAEAがその中立性と専門性を維持しつつ、効果的に対応していくためには、加盟国からの強固な政治的・財政的支援と、国際社会全体の核不拡散規範へのコミットメントが不可欠です。
技術革新とIAEAの進化:明日の核監視体制を築く
科学技術の急速な進歩は、IAEAが担う核不拡散の検証(保障措置)や原子力安全、そして核セキュリティといった活動のあり方にも大きな変革をもたらしつつあります。AI、ビッグデータ解析、先端センサー技術、そして量子技術といった新たなツールは、IAEAの監視能力を飛躍的に向上させる可能性を秘めている一方で、新たなリスクや課題も生み出しています。
AIがもたらすインテリジェント査察:未申告活動の早期検知へ
人工知能(AI)と機械学習(ML)の技術は、IAEAの保障措置活動において、特に未申告の核物質や核活動の兆候を早期に検知する能力を高める上で大きな期待が寄せられています。IAEAは、2022年に刊行した報告書「原子力の応用のための人工知能(Artificial Intelligence for Accelerating Nuclear Applications、仮称)」の中で、AIと高度なセンサー技術(環境サンプリング分析、衛星画像解析、オープンソース情報分析など)を統合し、膨大なデータを解析することで、従来は見逃されがちだった微細な異常やパターンを特定し、未申告核活動のリスクを評価する予測アルゴリズムの開発を目指す方針を示しています。
これにより、IAEAの査察官は、より効率的かつ効果的に査察計画を立案し、リスクの高い施設や活動にリソースを集中させることが可能になります。また、AIによる自動化されたデータ分析は、査察官の負担を軽減し、より高度な分析や判断に注力できるようになることも期待されます。いわば、「インテリジェント査察」の実現です。
しかし、AIの導入には、アルゴリズムの透明性や公平性の確保、機密情報の保護、そしてAIによる判断の誤りや悪用のリスクといった課題も伴います。IAEAは、これらの倫理的・技術的課題にも配慮しつつ、AI技術の責任ある活用を進めていく必要があります。
サイバーセキュリティの最前線:デジタル化された原子力施設のリスク
原子力施設における計測制御システムや物理的防護システムは、急速にデジタル化が進んでいます。これにより、運転効率の向上や情報管理の高度化といったメリットがもたらされる一方で、サイバー攻撃に対する脆弱性という新たなリスクも生じています。悪意のある第三者によって原子力施設の制御システムが乗っ取られたり、安全管理に関する重要なデータが改ざん・破壊されたりするような事態が発生すれば、深刻な原子力事故や核物質の盗難に繋がる恐れがあります。
IAEAは、このサイバーセキュリティの脅威を深刻に受け止め、加盟国に対し、原子力施設におけるサイバーセキュリティ対策の強化を強く推奨しています。IAEAが発行する「核セキュリティシリーズNo.17:原子力施設におけるコンピュータ・セキュリティ(Computer Security at Nuclear Facilities)」などの技術指針文書では、各施設がその特性に応じた包括的なコンピュータ・セキュリティ計画を策定し、サイバー攻撃の検知、防御、対応、そして復旧のための体制を整備することの重要性が強調されています。
また、IAEAは、サイバーセキュリティに関する国際的な訓練コースやワークショップの開催、専門家ミッションの派遣などを通じて、加盟国のサイバーセキュリティ対策能力の向上を支援しています。保障措置活動においても、IAEAが施設から収集・送信するデータの機密性や完全性を保護するためのサイバーセキュリティ対策は不可欠です。
量子暗号と核監視:ゲームチェンジャーとなるか?
量子技術の発展は、長期的には核不拡散の検証体制や核セキュリティのあり方に大きな影響を与える可能性があります。
-
量子鍵配送(Quantum Key Distribution: QKD): 量子力学の原理を利用して、盗聴が原理的に不可能な極めて安全な暗号通信を実現する技術です。IAEAと加盟国間、あるいはIAEAの査察官と本部間の機密情報のやり取りにおいて、QKDが将来的に活用されれば、通信の秘匿性を飛躍的に高めることができると期待されています。ただし、防衛省防衛研究所のブリーフィングペーパー「量子技術の軍事への応用」(2021年)などでも指摘されているように、QKD技術の長距離通信への応用やコスト面など、実用化にはまだいくつかの課題が残されています。
-
量子センサー: 量子効果を利用した高感度センサーは、微量の核物質や放射線を従来よりもはるかに高い精度で検知できる可能性があります。これにより、未申告の核活動の検知能力が向上したり、環境サンプリング分析の精度が向上したりすることが期待されます。
-
量子コンピュータ: 大規模で実用的な量子コンピュータが実現すれば、現在の暗号システム(RSA暗号など)を容易に解読してしまうため、国際的な情報セキュリティに深刻な脅威をもたらします。IAEAが扱う機密情報や、各国の核関連情報もその例外ではありません。一方で、量子コンピュータは、複雑な核物質の挙動シミュレーションや、新たな核物質検知アルゴリズムの開発など、核不拡散研究を加速させるツールとなる可能性も秘めています。
これらの量子技術は、まだ研究開発段階のものが多いですが、その潜在的なインパクトの大きさから、IAEAもその動向を注視し、将来の核監視体制やセキュリティ対策への応用可能性とリスクについて検討を進めています。これらの技術が「ゲームチェンジャー」となる日も、そう遠くないかもしれません。
用語解説:IAEAを理解するためのキーワード
国際原子力機関(IAEA)の活動や、それを取り巻く国際情勢を理解する上で、頻繁に登場するいくつかの専門用語があります。ここでは、特に重要なキーワードを分かりやすく解説します。
保障措置(Safeguards)とは?
保障措置(Safeguards)とは、IAEAが行う中核的な活動の一つで、各国が保有する核物質(ウランやプルトニウムなど)や原子力関連の施設・設備・技術が、平和的な目的から核兵器やその他の核爆発装置などの軍事目的に転用されないことを検知し、抑止するための一連の技術的・法的な検証システムのことです。
具体的には、加盟国がIAEAに提出する核物質の在庫量や移動に関する「申告」データと、IAEA査察官が現地で行う「査察」(核物質の計量、封じ込め・監視装置の確認、環境サンプリングなど)、そして施設に設置されたカメラやセンサーによる「遠隔監視」などを組み合わせて行われます。これらの活動を通じて、IAEAは各国が保障措置協定に基づく義務を遵守しているかを確認し、その結果を国際社会に報告します。保障措置は、核兵器不拡散条約(NPT)体制を支える上で不可欠な柱となっています。
SALTO(長期運転のための安全性側面評価)とは?
SALTO(Safety Aspects of Long Term Operation)とは、IAEAが提供する国際的なピアレビュー(専門家による相互評価)サービスの一つで、運転開始から長期間が経過した(あるいは長期運転を目指している)原子力発電所が、運転を安全に継続するための適切なプログラムや管理体制を有しているかを評価するものです。
世界の多くの原子力発電所が設計寿命を迎えつつある中で、高経年化した原発の安全性を確保し、可能な範囲でその運転期間を延長することは、エネルギーの安定供給や気候変動対策の観点から重要な課題となっています。
SALTOミッションでは、IAEAが組織する各国の経験豊富な専門家チームが、対象となる原発を訪問し、IAEAの安全基準や国際的なグッドプラクティスに照らして、設備の経年劣化管理、運転・保守体制、安全文化などを包括的に評価し、改善のための勧告や提言を行います。日本の原子力事業者も、このSALTOミッションを積極的に活用し、長期運転の安全性に対する国際的な信頼を得る努力を続けています。
ALPS処理水とは?
ALPS処理水(ALPS Treated Water)とは、2011年の事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所の敷地内で発生・貯蔵されている、放射性物質を含む汚染水を、多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)などを用いて浄化処理した後の水のことです。
ALPSは、汚染水に含まれる多くの放射性核種(セシウム、ストロンチウムなど62種類)を国の規制基準値を下回るまで除去することができますが、トリチウム(三重水素)という放射性核種は、水の構成要素である水素の同位体であるため、現在の技術ではALPSで分離・除去することが極めて困難です。
日本政府は、このALPS処理水を、国の規制基準の40分の1、WHOの飲料水水質ガイドラインの約7分の1という基準値以下になるまで大量の海水で希釈した上で、2023年8月から海洋への放出を開始しました。IAEAは、この海洋放出の安全性について、国際的な安全基準に照らした独立したレビューを行い、そのプロセスと結果を国際社会に公表しています。
まとめと今後の展望:IAEAの挑戦と日本の役割
国際原子力機関(IAEA)は、その設立から65年以上にわたり、原子力の平和的利用の促進と核兵器への転用の防止という二つの重要な使命を追求し、国際的な核不拡散体制と原子力安全の向上において、かけがえのない役割を果たしてきました。福島第一原発事故への対応やALPS処理水の安全性レビューといった近年の活動は、IAEAが直面する課題の複雑さと、その判断が持つ国際的な影響力の大きさを改めて示しています。
AIや量子技術といった先端テクノロジーの急速な発展は、IAEAの核監視・検証能力を飛躍的に向上させる可能性を秘めている一方で、原子力施設へのサイバー攻撃リスクの増大や、核関連情報の機密性確保といった新たな課題も突きつけています。IAEAがこれらの技術革新を効果的かつ責任ある形で取り込み、査察の高度化や核セキュリティの強化に繋げていけるかが、今後の大きな焦点となります。
2025年以降の国際情勢は、地政学的な緊張の高まりや「自国ファースト」主義の台頭など、不確実性を増しています。このような環境下で、IAEAがその中立性と実効性を維持し、核不拡散体制の「番人」としての信頼を保ち続けるためには、以下の三つの要素が鍵となると考えられます。
-
透明性の高いガバナンス: 意思決定プロセスや評価・検証活動の透明性を最大限に確保し、加盟国や国際社会からの信頼を得ること。
-
技術革新への迅速かつ的確な対応: 新たな技術がもたらす機会とリスクを的確に評価し、それをIAEAの活動に迅速に取り込んでいく柔軟性と専門性。
-
地域社会や多様なステークホルダーとの対話: 原子力に関する専門的な情報を分かりやすく発信し、市民社会や地域住民との建設的な対話を通じて、懸念や不安に応え、理解と信頼を醸成すること。
日本は、IAEAへの主要な財政的貢献国として、また高度な原子力技術と経験を持つ国として、これらのIAEAの挑戦に対し、今後も多大な貢献を果たすことが期待されています。資金面での支援継続はもちろんのこと、保障措置技術や原子力安全、核セキュリティ分野での技術協力、そして専門性の高い人材のIAEAへの派遣などを通じて、IAEAの能力強化を積極的に後押ししていく必要があります。
同時に、ALPS処理水問題で経験したように、科学的・技術的な評価の独立性を確保しつつ、国際社会の懸念に真摯に耳を傾け、透明性の高い情報発信と対話を粘り強く続けるという姿勢は、日本がIAEAとの関係においても、そしてより広範な国際社会においても、信頼されるパートナーであり続けるために不可欠です。第三者的な視点を確保するための国際的な枠組み作りや、その中での日本の建設的な役割は、今後ますます重要になるでしょう。IAEAの未来は、世界の平和と安全、そして人類と原子力の共存の未来そのものと深く結びついているのです。
参考リンク一覧
-
国際原子力機関(IAEA)公式ウェブサイト (英語):(URL)
-
外務省「国際原子力機関(IAEA)の概要」:(URL)
-
経済産業省 資源エネルギー庁「安全・安心を第一に取り組む、福島の“汚染水”対策①「ALPS処理水」とは何?「基準を超えている」のは本当?」:(URL)
-
IAEA “Fukushima Daiichi Status Updates” (英語): (URL)
-
IAEA “IAEA Safeguards: An Introduction | IAEA” (IAEA保障措置の概要、英語):(URL)
-
IAEA “Safety Aspects of Long Term Operation (SALTO)” (SALTOミッションに関する情報、英語):(URL)
-
IAEA “Incident and Trafficking Database (ITDB)” (核物質の不正取引等に関するデータベース、英語):(URL)
-
IAEA Publications “Artificial Intelligence for Accelerating Nuclear Applications” (英語):(URL)
-
IAEA Nuclear Security Series (核セキュリティに関するIAEAの出版物シリーズ、英語): (URL)
-
防衛省防衛研究所「ブリーフィング・メモ:量子技術の軍事への応用」(2021年12月):(URL)
-
KPMG “Geopolitical Risks Report” (英語): (URL)
(上記リンクは記事作成時点のものです。リンク切れや内容の変更についてはご容赦ください。最新の情報は各機関の公式サイト等でご確認ください。)
この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました
【PR】

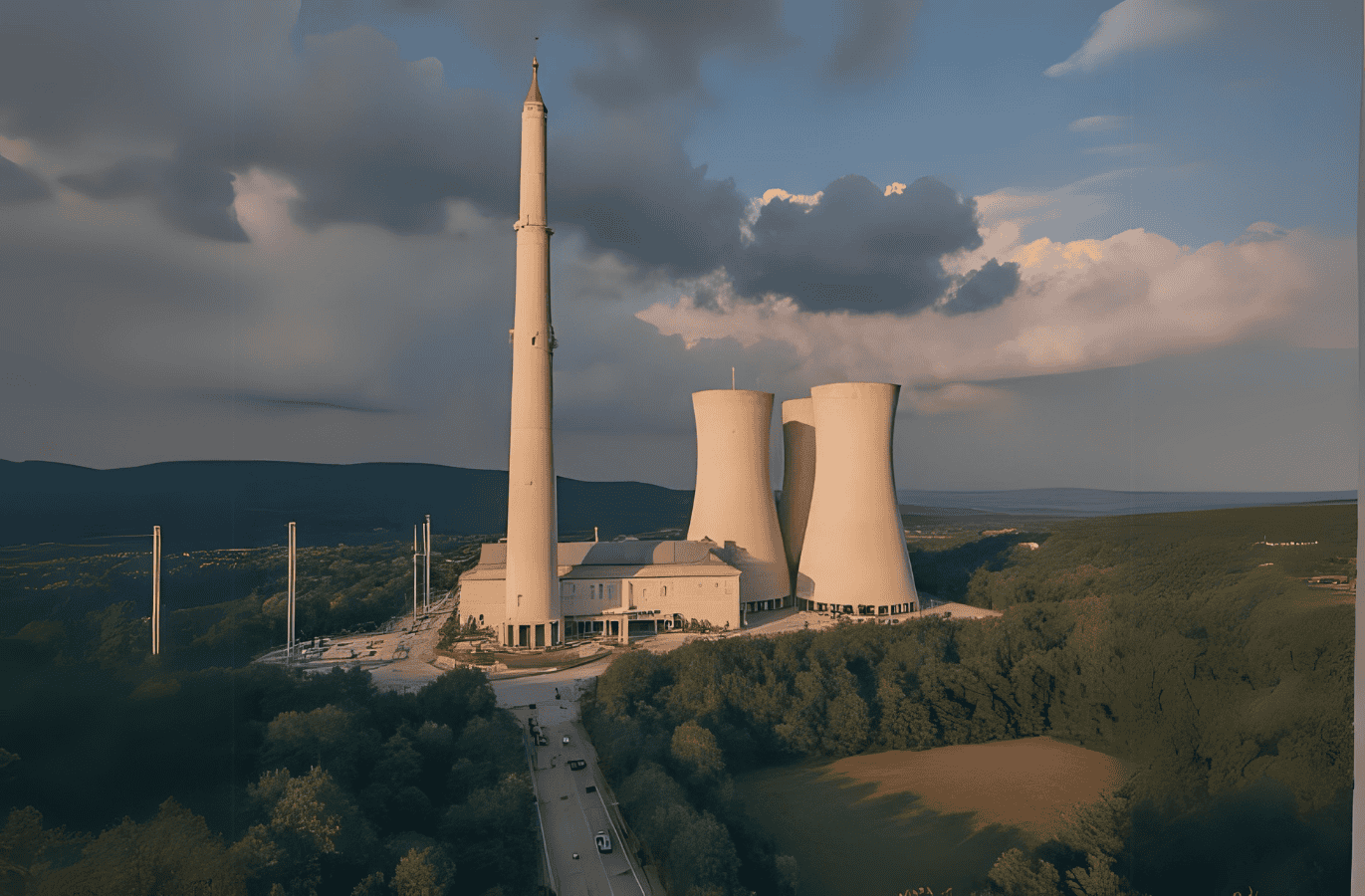
コメント