サステナブルファッション_フェアトレード 本記事では、国内外の主要ブランドによる最新の事例、業界全体の動向や市場規模の変化、技術革新と新ビジネスモデル、そして専門家の分析を通じて、サステナブルファッションの現在を専門家目線で深掘りします。
サステナブルファッション最前線:主要ブランドの最新事例とフェアトレードの展開
サステナブルファッションとは、環境や社会への負荷を抑え持続可能性を追求するファッションのことです。近年、気候変動や労働搾取への危機感から、この分野に世界中の注目が集まっています。主要ブランドは環境負荷の低減やエシカルな労働環境の整備、フェアトレード認証の取得など、さまざまな取り組みを加速させています。
主要ブランドのサステナブルファッションへの取り組み
大手ファッション企業はサステナビリティを経営戦略に組み込みつつあります。環境への配慮や公正な労働環境づくりに向けて、具体的にどのような取り組みを行っているのか、国内外のブランド事例を見ていきましょう。
環境負荷を減らすイニシアチブ:素材・製造の革新
ファッション業界は大量生産・大量廃棄による環境負荷が大きく、各社が素材や製造工程の革新によってその削減に挑戦しています。例えばアウトドアブランドのパタゴニア(Patagonia)は、環境負荷低減のパイオニア的存在です。同社はリサイクル素材やオーガニック素材を早くから採用し、自社製品の修理サービス「Worn Wear」を展開して衣服の寿命延長にも努めています。またパタゴニアは温室効果ガス排出削減にも注力し、「責任ある繊維調達」方針の下で再生ポリエステルなどの使用拡大を図っています。さらに特筆すべきは、製品の85%以上をフェアトレード認証工場で縫製しており、85,000人以上の労働者が恩恵を受けていると報告されています 。環境だけでなく労働者にも配慮する姿勢が一貫しています。
高級ブランドではステラ・マッカートニー(Stella McCartney)がサステナブル・ラグジュアリーを牽引しています。ステラ・マッカートニーは創業時からエコロジーと動物愛護を掲げ、ファー(毛皮)やレザーを使用しないポリシーを貫いてきました。近年では菌糸体から作るヴィーガンレザー「マイロ(Mylo)」など、次世代の代替素材にも積極的です。実際、ボルトスレッズ社の開発したマイロを世界で初めて衣服に採用し、キノコ由来の「はぎれゼロ」レザーによる衣服やバッグを発表しました 。こうした革新的素材の導入は、従来の素材生産による環境破壊を減らす可能性を示しています。一方で商業化のハードルもあり、量産化には引き続き技術開発が必要とされています。
スポーツウェア大手のアディダス(Adidas)やナイキ(Nike)もまた、素材循環と省資源に向けた取り組みを強化しています。アディダスは2017年に「2024年までにバージンポリエステル(新規生産のポリエステル)を全廃し、リサイクルポリエステルへ完全転換する」という目標を掲げました。その結果、2023年には自社製品で使用するポリエステルの99%をリサイクル由来にまで高め、2024年末までの目標達成にめどがついたと報告されています 。また海洋プラスチックごみを原料としたシューズ(Parleyコレクション)の展開など、廃棄物の有効活用にも努めています。
一方ナイキは生産工程での廃棄削減に注力しています。同社のフライニット(Flyknit)技術は編み込みによるシューズ製造法で、従来のカット&ソー製法に比べ約60%も材料廃棄を減らせるといいます 。フライニットを2012年に本格導入して以来、数百万ポンドもの素材廃棄を削減したとも報告されており、製造プロセス革新による環境負荷低減の好例となっています。
日本企業でも環境面での技術革新が進んでいます。大手アパレルのユニクロ(ファーストリテイリング)はロサンゼルスに「ジーンズ・イノベーション・センター」を設立し、デニム製造の持続可能化に取り組んでいます。従来ジーンズの色落ち加工には大量の水と化学薬品が必要でしたが、ユニクロはレーザー技術とオゾン処理を組み合わせた新工程を開発し、ジーンズ仕上げ工程の水使用量を従来比で平均90%以上、最大99%削減することに成功しました 。2018年秋冬からこの「ブルーサイクルジーンズ」を商品化し、大量生産品でも水資源節約が可能であることを示しています。
同じく日本発の素材イノベーションとして、スタートアップ企業スパイバーの人工たんぱく質素材「ブリュードプロテイン(Brewed Protein)」があります。これはクモの糸に似た構造の繊維を微生物発酵で生産する技術で、2021年にはザ・ノース・フェイスと協業したジャケットにも採用され話題となりました。こうした国内外の技術革新は、ファッション製造の環境負荷を飛躍的に下げるポテンシャルを秘めています。
平均すると日本では1日あたり大型トラック約120台分の衣服が焼却・埋立処分されており、年間では約45万トンに上る 。この廃棄量削減がサステナブルファッションにおける重要課題である。
エシカルな労働環境とフェアトレード認証の推進
サステナブルファッションのもう一つの重要な柱が、サプライチェーンに関わる人々の労働環境改善や公正な取引=フェアトレードの推進です。ファッション製品の多くは途上国の縫製工場で生産されており、安価な労働力に依存した構造が長らく問題視されてきました。近年は消費者やNGOの監視が強まり、ブランド側も労働者の人権と福祉に配慮した調達を掲げ始めています。
フェアトレード専門ブランドの草分けとして知られるピープルツリー(People Tree)は、その代表的存在です。ピープルツリーは1991年に日本で設立されて以来、一貫して開発途上国の生産者と対等な関係を築き、適正な賃金を支払うフェアトレードファッションを展開してきました。オーガニックコットンなど天然素材の手仕事による衣料を中心に、雑貨や食品も扱い、すべての製品に世界フェアトレード連盟(WFTO)の保証ラベルを付与しています 。これは原材料の調達から縫製に至るまで、公正な取引と適正労働条件が守られていることを保証するものです。ピープルツリーのような専門ブランドは規模こそ大手に比べ小さいものの、30年以上にわたりフェアトレードの重要性を訴求し続け、エシカル消費の土壌作りに大きく貢献しています。
大手ブランドもフェアトレードや労働環境の改善に動き出しています。先述のパタゴニアは、環境のみならず社会的責任にもコミットしており、2020年代には製品ラインの90%以上をフェアトレード認証工場で製造するまでになりました 。パタゴニアの製品についている「Fair Trade Certified™ Sewn」のタグは、消費者が購入を通じて縫製労働者の生活向上を支援できることを示しています。同社は2014年からフェアトレード認証を導入し始め、2019年時点で既に製品の約70%が認証工場製となっていた ほどで、アウトドア業界における倫理的調達の先駆けといえます。
ファストファッション勢も無視できません。H&Mは「サステナビリティはもはやオプションでなく必須」と公言し、サプライヤーの労働環境監査や労働者への教育プログラムを実施しています。また2020年には「サステナブル調達責任者」を新設し、生産国ごとに賃金支払い状況をチェックする体制を強化しました。
ZARA(インディテックス社)やGAPも、生産工場リストの公開など透明性向上に踏み出しています。ただし、これら大手による取り組みには「十分ではない」「実効性が伴っていない」といった批判も依然あります。例えばバングラデシュやカンボジアの縫製工場では、依然として低賃金や長時間労働が蔓延しているとの指摘があり、ブランド側の更なる努力が求められています。
日本企業では、先述のユニクロも含め、労働環境の改善に着手する動きがみられます。ユニクロは2015年以降、自社委託工場の監査結果を年次報告書で公開し、問題があれば契約打ち切りも辞さない姿勢を打ち出しました。また大手流通のイオンはプライベートブランドでフェアトレード認証コットンを採用した衣料品を販売し、消費者に公平な取引で作られた商品の選択肢を提供しています。さらに、日本発の若者向けブランドでもインドの手織物を適正価格で仕入れるなど、小規模でもエシカルを志向する例が増えてきました。
総じて、ブランド各社の取り組みは環境面と社会面の両立を目指す方向に進んでいます。とはいえ、その深度やスピードは企業によって様々で、先進的な企業がある一方、表面的なアピールに留まり「グリーンウォッシング」と批判されるケースもあります。後述する専門家の指摘にもあるように、業界全体で実効性の高い取り組みへと底上げしていくことが課題となっています。
業界動向と市場規模の変化
サステナブルファッションは一部の志あるブランドだけの試みから、業界全体のトレンドへと変貌しつつあります。その市場規模は年々拡大し、消費者の意識にも大きな変化が見られます。このセクションでは、市場の成長動向と消費者マインドシフトについてデータを交えて考察します。
市場拡大とサステナブルファッションの位置づけ
持続可能なファッション市場は、世界規模で急成長しています。まだ従来のファッション市場全体と比べれば小さいものの、近年の成長率は著しく、今後も拡大が予測されています。ある推計によれば、2023年時点で約7〜8億ドル規模(約1兆円弱)だった世界のサステナブルファッション市場は、2030年までに約4倍の28.5億ドル規模に達する見通しとされています 。年平均で20%前後という極めて高い成長率です。また別の試算では、2024年時点の持続可能ファッション市場は約81億ドルで、2033年には331億ドルに達すると予測されており、こちらも年22.9%もの伸び率が見込まれています。数字の幅はありますが、いずれの予測も今後10年で数倍規模に拡大するトレンドを示しています。
市場全体に占める比率も少しずつ高まっています。2010年代初頭には1%程度に過ぎなかった世界衣料品市場における持続可能系商品の売上比率は、2020年代半ばには6%程度に達するとの分析があります 。6%という数字は依然として一桁台ですが、10年前と比べると大きなジャンプです。裏を返せば、まだ90%以上の市場が従来型ファッションで占められているため、サステナブルファッションの伸びしろは極めて大きいとも言えます。
この成長を牽引している要因の一つは消費者の需要増です。次の節で詳述するように、特にミレニアル世代やZ世代を中心に環境・社会配慮型の商品を選びたいという意識が高まっており、企業側もそれに応える形でサステナブルな商品ラインを拡充しています。またもう一つの要因は規制や投資の動向です。欧州を中心にサステナビリティ開示の義務化や廃棄規制など法整備が進み、ファッション企業にとってサステナビリティ対応は「企業評価」に直結する重要事項となりました。投資家もESG(環境・社会・ガバナンス)重視の観点から、サステナブルなビジネスモデルを持つ企業に注目しています。こうした背景から、大手ブランドも市場の方向性を見据えて持続可能な商品・サービス開発に資源を投入するようになっています。
一方で、サステナブルファッション市場の成長には地域差もあります。北米や欧州では消費者意識が高く市場拡大が顕著で、ある調査では世界の持続可能アパレル市場のシェアの40%以上を北米が占めるとのデータもあります。これに対し、日本を含むアジアでは欧米に比べ認知・需要が遅れているとの指摘もあります。しかしアジアでもここ数年で各国メディアがファッションと環境問題を盛んに報じるようになり、追随する形で市場の伸びが始まっています。特に中国の若年層や日本の都市部の消費者がエシカル消費に関心を寄せ始めており、グローバル企業にとってもアジア市場でのサステナブル商品の投入は無視できない状況です。
消費者の意識変化と購買行動
サステナブルファッション市場拡大の原動力となっているのは、他ならぬ消費者意識の変化です。過去10年で、「安ければ多少環境に悪くても構わない」という考えから、「多少高くても環境や社会に優しい商品を選びたい」という考えへ、特に若い世代を中心にマインドシフトが起きています。
国際的な調査ではこの傾向が明確に現れています。ニールセンの調査によれば、世界の消費者の66%が環境や社会に配慮するブランドの商品により多く支払っても良いと回答しており、その割合は2013年の50%から着実に増加しています 。ミレニアル世代に限ればその比率は75%に上るとのデータもあり、若年層ほどサステナビリティ志向が強いことがわかります。また消費者の約67%がブランド選択時に持続可能性を重要な要素と考慮するとも報告されており 、もはやサステナブルであること自体がブランド競争力の一部となりつつあります。
日本国内でも徐々に意識は高まっています。環境省の調査では、「環境や社会に配慮したファッションを取り入れたい」と考える人が全体の70%以上にのぼったとの結果が出ています 。特に「地球環境保護に参加したいから」「社会貢献に興味があるから」といった理由でサステナブルな服を選びたいと答える人が多く、ファッションを通じたポジティブな行動に関心を持つ層が増えていることが伺えます。またZ世代(10〜20代)では、「安さやデザインに惹かれて買ってしまうけど心の中では環境に罪悪感を覚える」といった「ごめんね消費」を経験したことがある人が半数以上という調査もあり、若年層の間でファストファッションへの葛藤が生まれています 。こうした葛藤がいずれ行動の変化につながる可能性があります。
もっとも、日本の場合は意識と行動のギャップも指摘されています。消費者庁の意識調査では、実際に衣服を購入する際にサステナブルな取り組みを「特に考慮しない」と答えた人が過半数を占めたという結果もあります。頭では大事だと分かっていても、いざ買い物では価格やデザインを優先してしまう人が多いという現状です。このギャップを埋めるには、消費者教育や情報提供に加え、サステナブルな商品の魅力(デザイン性や価格競争力)の向上が必要でしょう。
消費者行動の変化で注目すべきもう一つの潮流が、リセール(再販売)やリユース市場の拡大です。新品ではなく中古品やレンタルでファッションを楽しむ動きが広がっており、これもサステナブルファッションの一環と見なされています。日本ではフリマアプリのメルカリが牽引役で、2022年には物価高騰下で節約志向が高まったこともあり、メルカリが創業以来の最高業績を記録しました。これは消費者が「今あるものをより長く使う」方向へ価値観をシフトさせつつある兆候ともいえ、従来の「大量生産・大量消費」モデルからの転換が進んでいることを示しています。
海外でも中古衣料の市場規模が拡大しています。特に米国では高品質な中古衣料を扱うThredUpやThe RealRealといったサービスが人気化し、2020年代半ばには中古衣料市場がファストファッション市場を上回る勢いとも言われます。またレンタルファッションも定着しつつあり、Rent the Runway(米)やLe Tote(米)、さらには日本のairClosetなど、月額制で洋服を借りるサービスの利用者も増加しています。これらのサービスは服の所有ではなく利用に価値を見出すもので、クローゼットの循環を促進しています。このように消費者の選択肢が多様化する中で、「新品を買う」以外のファッション消費が伸びていることも、広義にはサステナブルファッション市場の拡大と捉えることができます。
技術革新と新たなビジネスモデル
サステナブルファッションの進展には、技術革新とビジネスモデルの変化が大きな役割を果たしています。リサイクル技術の発展や画期的な新素材の登場、さらには循環型経済を志向したサービスやデジタル技術の活用など、ファッション産業は新たなステージに突入しつつあります。このセクションでは、それら革新的な動きをケーススタディを交えて紹介します。
リサイクル素材と次世代の革新的素材
従来はごみとして廃棄されていた資源を再生利用し、新たな素材や製品に生まれ変わらせる技術が飛躍的に進歩しています。特にペットボトルや古着などから再生ポリエステル繊維を作る技術は既に実用段階にあり、多くのブランドがリサイクルポリエステル製品をラインナップしています。前述のアディダスのように、バージンポリエステルを完全になくし100%リサイクル品に置き換えるという企業も登場しています 。またH&MやZARAは、使い終わった衣類を回収して再生繊維に転換する試みを一部製品で始めました。H&Mはスウェーデン企業リニューセル(Renewcell)の協力で、廃棄衣料から再生したセルロース繊維「Circulose」を用いた服を発売しています。ZARAもスペイン本国で古着回収を推進し、自社の新作にリサイクル素材を組み込む割合を毎年増やしています。
さらなる新技術として注目なのが、廃棄物や二酸化炭素から繊維を生み出す試みです。例えば米スタートアップのランザテック(LanzaTech)は工場の排気ガスなどに含まれるCO₂や一酸化炭素を微生物発酵によってエタノールに変換し、そこからポリエステルの原料を作り出す技術を開発しました。ファストファッション大手のZARAは2022年、この技術で製造したポリエステルを20%含むドレスを限定販売し、工業排出ガスから作った生地を初めて衣料化しました。廃ガス由来とは思えない美しいドレスは話題を呼び、廃棄物リサイクルの新たな可能性を示しました。
一方、新素材の開発も盛んです。前述のキノコ由来レザーの他にも、植物由来の代替レザーとしてパイナップルの葉から作る「Piñatex」や、サボテン由来の「Desserto」などが登場し、既に一部製品に採用されています。合成生物学を駆使した培養繊維の分野でも、蜘蛛の糸や動物由来コラーゲンを人工培養して繊維化する研究が進んでいます。これらの中には量産コストや耐久性の課題が残るものもありますが、ファッション各社は競って投資・提携を行い、将来のゲームチェンジャーを模索しています。
また循環型素材として**リジェネラティブ・カリクーラム(Regenerative Agriculture)**由来の繊維も注目されています。これは土壌や生態系を再生しながら生産されるコットンやウール等で、通常のオーガニックより一歩進んだ環境貢献を謳うものです。パタゴニアやステラ・マッカートニーは一部製品に再生農法コットンを採用し始めました。今後こうした「カーボンネガティブ」(生産過程で温室効果ガス排出より吸収が上回る)素材が増えてくれば、ファッション産業全体の環境フットプリント低減に大きく貢献するでしょう。
循環型経済へのシフト:リペア・リユース・レンタルのビジネスモデル
ファッションの循環型経済(サーキュラーエコノミー)を推進する新たなビジネスモデルも数多く生まれています。その中心となるのが、リペア(修理)・リユース(再使用)・リサイクルを前提にしたサービスの展開です。
先駆者的存在であるパタゴニアの「Worn Wear」は、顧客が使い古したパタゴニア製品を無料または低価格で修理し長持ちさせる仕組みで、大変人気を博しています。欧米では購入後数十年経ったジャケットを修理してもらい再び着るといったエピソードも珍しくなく、「直せば着られるのに捨てるなんてもったいない」という意識を浸透させました。さらにパタゴニアは不要になった自社製品を下取りして中古品として販売する取り組みも行っており、メーカー自ら中古市場に関与するモデルとして注目されています。
近年はファストファッション企業も自社製品の回収・再販を試み始めました。例えばZARAは2022年にイギリスで「Zara Pre-Owned」という中古売買・修理プラットフォームを立ち上げ、顧客がZARA製品を売買したり有償で修理依頼できるサービスを開始しました。H&Mも店舗での古着回収は以前から実施していますが、2023年にはドイツなどで自社ブランド古着専門のオンラインストアをオープンし、リユース市場に乗り出しています。これらの背景には、「売り切りで終わり」ではなく「製品寿命の延長まで責任を持つ」ことが企業の新たな責務と見なされ始めたことがあります。
レンタルはユーザー視点での循環型モデルです。上記のようにレンタル専業の新興企業も台頭していますが、伝統的ブランドでもレンタルサービスを試験導入する例が出てきました。例えばH&Mは旗艦店で期間限定のレンタルポップアップを開いたり、米アーバンアウトフィッターズは自社ブランド服を月額制で貸し出すサービス「Nuuly」を開始しています。日本でも百貨店のワールドやオンワードがフォーマルウェアのレンタル事業を手掛けるなど、従来販売だけだった企業がサブスクリプション型の貸出に参入しつつあります。
レンタルやリユースが環境に与える効果は定量的にも示されています。環境省の実証事業による試算では、ファッションレンタルを活用することで通常の新品購入モデルに比べCO2排出量を19%、廃棄物排出量を27%削減できるとの結果が報告されました 。もちろんレンタル品のクリーニングや配送による環境負荷もありますが、それを勘案してもトータルではメリットがあるという分析です。今後物流の低炭素化や洗濯技術の省資源化が進めば、さらに効果は高まるでしょう。
デジタル技術の活用によるトレーサビリティと効率化
デジタル技術もサステナブルファッションを支える重要なツールです。特にブロックチェーンなどを用いたサプライチェーンのトレーサビリティ(追跡可能性)確保は、大手ブランドが競って導入を進めています。ラグジュアリーブランドのステラ・マッカートニーはブロックチェーン基盤のプラットフォーム「Provenance」と提携し、自社サプライチェーンの情報を消費者に開示する試みを行いました。その結果、生産履歴を遡ることで原料調達から縫製に至るまで倫理的に作られた商品であることを証明し、ブランドへの信頼性向上につなげています 。またルイ・ヴィトンなどを傘下に持つLVMHグループも業界横断のブロックチェーン「Aura」を構築し、高級品の真贋証明や素材由来証明に活用しています。将来的にはデジタルパスポートと呼ばれる製品ごとの電子タグが普及し、消費者はQRコードなどをスキャンするだけでその服の生い立ち(どこで誰が作り、どんな素材が使われているか)を確認できるようになると期待されています。
デジタル技術はさらに、在庫管理や需要予測の高度化にも役立っています。AI(人工知能)を用いてトレンド予測や適正在庫を分析することで、売れ残りの過剰生産を抑える動きが始まっています。ファッション業界では毎年大量の在庫が廃棄処分されていますが、AIを活用した精緻な需要予測により無駄な生産を減らせれば、環境負荷低減とコスト削減の両面でメリットがあります。また3Dデザインやバーチャル試着の普及も、生産効率と廃棄削減に貢献します。CAD上で3Dモデルを作成しサンプル検討を行えば、フィジカルな試作品を何度も作り直す必要が減りますし、消費者もオンラインで試着体験できればサイズ間違いによる返品(そして返品商品の焼却処分)の減少につながります。
さらに、eコマース上で環境負荷の見える化を行う取り組みも増えています。英ブランドのレフォーメーション(Reformation)は、自社商品の製造に伴うCO2排出量や水使用量を商品ページに「環境スコア」として表示しています。オールバーズ(Allbirds)というシューズブランドも全製品にカーボンフットプリント(CO2排出量)を明記し、消費者が環境コストを意識した選択をできるようにしています。このような透明性の確保は消費者教育にもつながり、結果的によりサステナブルな商品の需要を喚起する好循環を生み出します。
専門家の視点と分析
サステナブルファッションの現状と今後について、専門家や有識者からはさまざまな意見が出されています。業界レポートや学術的な分析から浮かび上がる課題と展望を見ていきましょう。
業界レポートが指摘する課題:進捗の停滞とリスク
ファッション業界全体を見ると、持続可能性への取り組みは確実に進展しているものの、その速度や実効性に対する懸念も少なくありません。コンサルティング企業マッキンゼーや業界誌ビジネス・オブ・ファッション(BoF)の報告によれば、2020年代半ばに入りファッション企業の経営層がサステナビリティを最優先課題と捉える割合が減少傾向にあるといいます。具体的には「持続可能性を今後の成長リスク上位3つに挙げるファッション業界経営者」は、2024年には29%いたのが2025年には18%にまで低下する見通しとの調査結果が出ています 。景気動向やコスト増の圧力から、一部企業はサステナビリティ投資に慎重姿勢を強めているとの分析です。この数値は「サステナブルファッションへの熱意が一時より冷めつつあるのではないか」という懸念を呼び、専門家は進捗の停滞を警戒しています。
また、これまで触れてきたブランドの取り組みに対しても、「十分に根付いていない」という厳しい指摘があります。例えば持続可能素材の採用について、グローバルファッションアジェンダ(Global Fashion Agenda)の報告では「現在のペースでは業界全体の環境負荷削減目標に到底追いつかない」とされています。さらにリサイクル率の低さも大きな課題です。世界で生産される繊維のうち、新しい衣料にリサイクルされるのはわずか1%未満に過ぎず、残りは焼却・埋立や他用途へのダウンサイクル(工業用ウエス等)に留まっているとの統計があります。これはつまり、多くの衣服が実質使い捨てられている現状を意味します。また世界全体では毎秒トラック1台分の衣類が焼却または埋め立て処分されているとも言われ 、廃棄問題の深刻さが浮き彫りです。
社会的側面でも課題は山積しています。2013年のラナプラザ崩壊事故(バングラデシュの縫製工場ビル倒壊で1,100名以上が犠牲)以降、労働環境改善への機運が高まり、バングラデシュでは「労働安全協定(アコード)」が結ばれるなど前進はありました。しかしグローバルサプライチェーン全体で見れば、依然として低賃金労働や不安定雇用が横行しています。ILO(国際労働機関)の推計では、衣料品産業の労働者の多くが依然として生活賃金(生活に必要な十分な賃金)を得られていません。フェアトレード認証や企業独自のCSRプログラムは増えたものの、恩恵を受けるのは一部に留まっているのが実情です。専門家からは「環境面ばかり注目されがちだが、ファッションのサステナビリティには人権・労働の問題解決が不可欠」との声も上がっています。
加えて、グリーンウォッシング(見せかけだけの環境配慮)への警戒も必要です。消費者庁は2022年に景品表示法の観点から「エコ」を謳う広告の実態調査を行い、ファッション業界にも誤認を招く表示がないかチェックを始めました。一部には「持続可能素材使用!」とうたいつつ実際には全製品の数%しか該当しないケースや、根拠不明なエコマークを独自につけている例も指摘されています。こうした不誠実な対応は消費者の信頼を損ね、業界全体のサステナビリティ推進にも水を差しかねません。専門家は「企業は透明性を持って事実を示し、誠実に取り組むこと」が肝要だと強調しています。
今後の展望と必要なアクション:専門家が描く未来
持続可能な未来のファッション産業を実現するには、どのような変革が必要なのでしょうか。サステナブルファッションの先駆者であるピープルツリー創業者のサフィア・ミニー氏は、「時間がない」という強い危機感を示しています。ミニー氏は2021年の国際フォーラムで「このままでは2050年までにファッション業界が世界の温室効果ガス排出の25%近くを占めるようになってしまう」と警鐘を鳴らし、生産と消費を今から75〜95%削減するような“急進的”な変革が必要だと訴えました 。単なる効率化や部分的な素材転換では不十分で、ファッションそのものの在り方を抜本的に見直す必要があるという主張です。またミニー氏は「化石燃料由来の素材を排し、再生農業で作られた天然繊維やリサイクル素材へ移行すること」「発展途上国の小規模農家や職人をサプライチェーンの中心に据え、社会的公正を実現すること」の重要性を強調しています 。大量生産・大量消費モデルから地域分散型・労働集約型のモデルへのシフトが、環境にも人にも優しい未来につながるとの展望です。
同じフォーラムで、スペインのエコファッションブランドエコアルフ(ECOALF)創業者のハビエル・ゴイェネチェ氏は「ファッションはもう『見た目が良ければいい』だけでは許されない。正しいことをして、それに誇りを持てるものでなくては」と述べ 、企業側と消費者側双方の意識変革を呼びかけました。ゴイェネチェ氏は消費者に対して「もう20枚もTシャツはいらない。量より質を、責任を持って買うべきだ」と訴え (Why fashion needs a sustainability revolution | World Economic Forum)、必要以上に買わないスタンスを促しています。これは消費行動の面で“Less is more”(より少なく買い、長く大切に使う)哲学を広めようとするものです。実際、欧米では古着をリメイクして着たり、ごくお気に入りの少数の服を着回す「ミニマリスト・ファッション」も若者に広がりを見せています。専門家らは、企業努力だけでなく私たち一人ひとりのライフスタイルの見直しもまた不可欠だと指摘しています。
政策面でも将来像が描かれています。EU(欧州連合)は2030年までに「持続可能で循環型のテキスタイル産業」を実現すべく包括戦略を打ち出しました。その中では「2030年までにEU市場で販売される繊維製品をすべて耐久性・修理可能・リサイクル可能かつ可能な限りリサイクル繊維由来にし、有害物質フリーで、環境・社会に配慮して生産されたものにする」という目標が掲げられています。
また使い捨て的なファストファッション文化を過去のものにするとも明言しており、売れ残り衣料の焼却禁止や製造者責任制度(EPR)の導入など具体策が検討されています。これが実現すれば、欧州向けに商売をするグローバル企業はビジネスモデルを大きく転換せざるを得ません。日本でも経産省が2023年に「サステナブルファッション推進検討会」を立ち上げ、EUに倣った政策の必要性を議論し始めました。規制による後押しが進めば、業界全体の底上げにつながるでしょう。
最後に、専門家たちは「コラボレーション」の重要性を口を揃えて強調します。素材メーカー、アパレル企業、リサイクル業者、スタートアップ、消費者、行政——ファッションのバリューチェーンに関わるすべての主体が連携し、イノベーションを共有していくことが求められます。例えば前述のキノコレザーや廃棄ガス由来ポリエステルの事例も、スタートアップと大手ブランドのコラボが実を結んだものです。また業界標準の策定や情報共有プラットフォームづくりも欠かせません。
ひとつの企業だけで取り組んでも限界がある問題(例えば化学繊維のリサイクル技術開発など)は、企業連合や官民プロジェクトとして進めるべきだという意見も出ています。幸いファッション業界にはサステナブル・アパレル連合や繊維交換所など協業の枠組みが存在し、環境測定指標(Higgインデックスなど)の標準化も進みつつあります。今後さらに垣根を越えた協調体制を強化することで、持続可能な未来へのロードマップがより現実味を帯びてくるでしょう。
おわりに:持続可能な未来に向けて
サステナブルファッションとフェアトレードの潮流は、単なるブームやマーケティング上の付加価値ではなく、ファッション業界の構造転換そのものと言える段階に入っています。主要ブランドの取り組みは環境・社会両面で深化し、市場は拡大し続け、技術革新が次々に生まれ、専門家からはより大胆な改革が提言されています。とはいえ課題も多く、業界全体で解決すべき問題が山積しています。
しかし、消費者の私たち一人ひとりが意識と行動を少し変えるだけでも、その積み重ねが業界を動かす原動力となります。企業・消費者・政策立案者などあらゆる立場が協力し合い、ファッションの未来を持続可能な形にアップデートしていくことが求められています。サステナブルファッションは未来のスタンダードとなるべく、今まさにその最前線で進化を遂げているのです。
この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました
【広告】


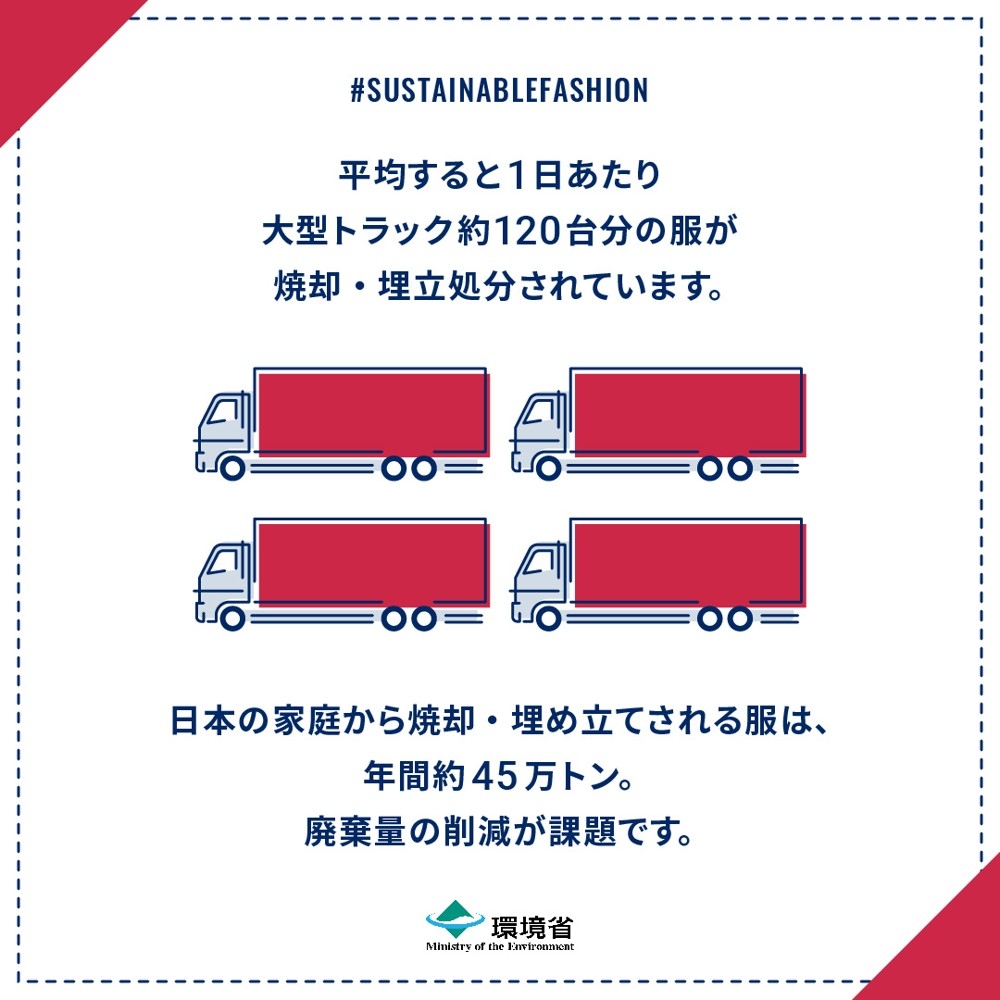
コメント